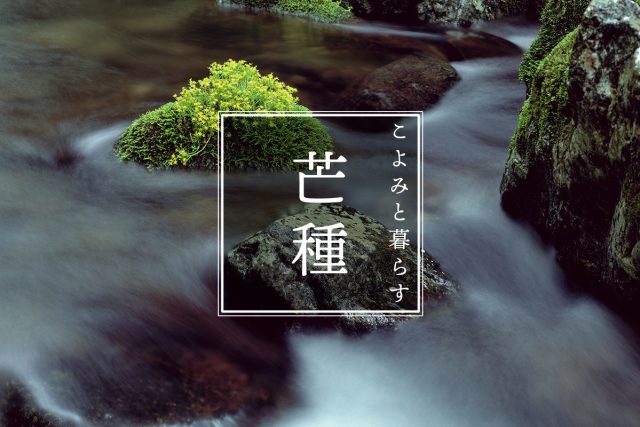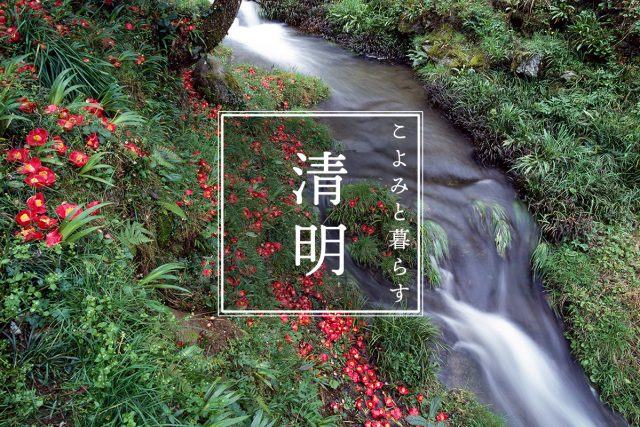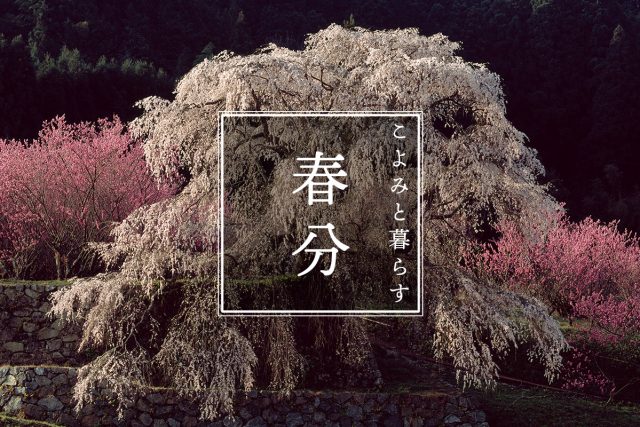こよみと暮らす
こよみと暮らす こよみと暮らす 第七回『夏至』
いらかの波と雲の波。という歌いだしではじまる、鯉のぼりの歌を思い出すような風景です。奈良市の中心部からほど近い歌姫町。写真は、旧街道沿いの古民家の屋根を捉えています。もともと平城山丘陵と呼ばれるこの付近一帯では、瓦に必要な粘土や燃料が豊富で、瓦窯跡がいくつも残っています。初夏の日差しに照らされて、よく乾いた瓦。ちょっとお布団でも干したくなるような屋根です。こんなふうにカラッとした天気の日が、この季節は特に貴重に思えてきます。 ...